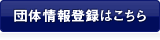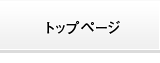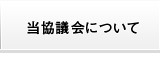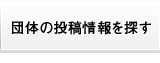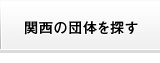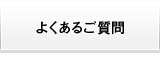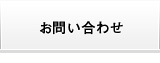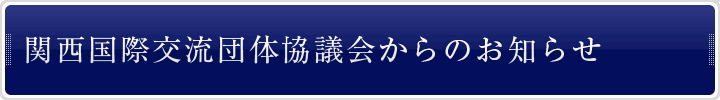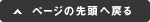外国人母子支援ネットワーク形成事業(*注1)では、9月3日(月)に、第2回研究会夜の部が実施され、「にほんごサポートひまわり会」より斎藤裕子代表にお越しいただき、お話をおうかがいしました。
*注1平成24年度大阪府新しい公共支援事業「NPO等の活動基盤のための支援事業」マーテル外国人母子支援ネットワーク形成事業
参考:「にほんごサポートひまわり会」
http://www.himawarikai200311.org/
8月9日の第1回研究会夜の部で、外国にルーツのある子どもたちにとって「居場所」があることが大切なこと、また子どもの表面的な言動のみに着目するのではなく家庭や家族等々にも目を向けないといけないこと、そして地域でどう支えるかについて意見が交わされたため、こうした分野で取り組まれている斉藤様をお招きすることになりました。
参考:第1回の様子はこちらから↓https://www.interpeople.or.jp/info/2012/08/post.html

お話では、まず、外国にルーツを持つ子どもたちが直面している状況についてわかりやすく説明がありました。
・来日年齢や母国で受けた教育年数によって状況が違うこと。
・全ての子どもが自動的にバイリンガルになるわけではないこと。
・「今ここ」の会話がそれなりに成立するために、子どもが抱えている苦しみや困難さが周囲に理解されにくく、我侭等性格や親のしつけの問題と歪曲されかねないこと。
・学校で使う語彙と家庭で使う語彙との大きなギャップがあること。
・親の日本語習得度によっては、子どもの日本語能力を過度に高く評価し、頼りきっている状況もままあること。
その他、ここでは紹介しきれないほど、エピソードを交えながら子ども達親達から見える世界についてお話いただきました。
そして、これらの状況に置かれている親子のニーズに寄り添うように活動をされている「にほんごサポートひまわり会」の様々な取り組みについて報告がありました。会が大切にされていることは、会のリーフレットに以下のように記載されています。
・高齢者、子ども、非識字者、乳幼児連れの人など、日本語学習の機会が得にくい人が学びやすいように
・学習者のニーズに応えるよう努力する
・地域の中の日本語教室として、地位との連携、地域への発信など、「地域」を意識した活動
具体的には毎週土曜日に、個々人のニーズに寄り添った日本語教室や、子育て日本語サロン、外国から来た子どものための学びのサポート等をボランティアの皆様と実施されています。また時々、盆踊り講習会やたこ焼きパーティー等各種イベントも実施されています。

報告を聞いた後の参加者の感想としては、参加者も前々から感じておられた問題点を明確に整理いただけた感動と、どういう活動が必要か重要かについて考えさせられた旨の声が多数挙がりました。その一部を以下のとおり御紹介します。
「かかわりをもっている外国人の家庭の子どもの問題ととても重なります。」
「子どもたちがかかえる課題解決には、いろんな(たくさん)の方とのつながりが大切だと改めて感じた。」
「外国にルーツを持つ親子で、支援が必要な方が大勢いることを改めて認識。」
「子どもと親の関係、言葉についてなるほどと思うことがありました。」
「日本語を母語としない子どもへの教育の難しさ」
「日本語にしろ、そうでないにしろ、知識のベースとなるものがとても大切だと分かった。」
「しっかり日本語を学習することの大切さ、まわりのサークル、地域で支える二輪が大切。」
「親に頼れない子ども達をちょっと支えることで学ぶこと、体験出来るとわかる。会の活動が居場所になっている。」
「このような会がたくさんできるといいですね。」
「イベントで他VOグループと協力していること。すばらしい!幅広い活動が可能!!」
「きめ細やかな日本語教室で外国人の子ども達の居場所であると感じた。」
「子どものアイデンティティの確立が気になりました。ロールモデルは重要だと思いました。」
そして参加者の中からは
「学びのサポート」
「子ども(+母親)への日本語教室を各区に一つはつくれれば」
「子育てサロンのような場」
「日本人から学ぶこと大切と共に外国人が外国人に日本語を教える(日常のこと、学校からのお知らせ)」
といったことに取り組みたいという声が上がりました。
次回以降、是非皆さんと共に議論を重ね、具体的な計画を立てていきたいと思います。
参加くださいました皆様、ありがとうございました。
次回は10月11日(木)に昼の部、10月15日(月)に夜の部を予定しています。
詳細は追って本ブログにアップいたしますので、皆様是非御参加下さい。初めての方も大歓迎ですので、是非お越し下さい。